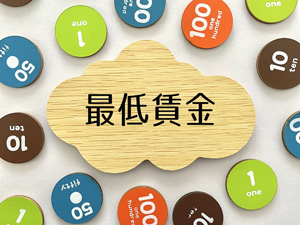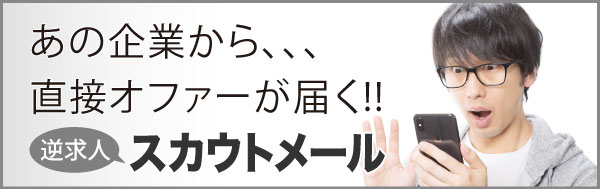高年齢求職者給付金って?手続きや受給資格の解説

この記事の目次
近年は働き方改革などの取り組みにより、高齢者の雇用環境拡充で改善が実施されています。それによって様々な制度改革も進んでいますが、その中の1つが高年齢求職者給付金です。
高年齢求職者給付金を初めて聞く方も少なくないでしょう。しかし、65歳を過ぎて働く方にとっては、一つのセーフティネットとして働くのです。もし老後も働きたいと考えている方は、制度の仕組みや受給条件、給付金の受給方法について知っておく必要があります。
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の労働者を対象とした失業保険をいいます。65歳未満の労働者の場合、離職後は雇用保険加入期間によって失業保険が受け取れます。しかし、65歳を過ぎると対象から外れるため、失業保険の代用として作られた制度が高年齢求職者給付金です。
あくまで給付金のため所得税は課税されませんし、受給の回数制限もありません。年金の支給額にもいっさい影響が及ばないため、年金を受給しつつ、安心して次の仕事を探せます。
年齢の上限も定められていません。例えば75歳の方や80歳の方でも、後述する受給条件を満たしている方は、給付金を受け取ることができます。そのため、生涯現役という選択肢も現実味が増すでしょう。これまで以上に働きやすい環境が整ったといえます。
高年齢求職者給付金は、失業保険の代替制度に近いですが、給付金額は主に前職の収入で決まります。ただし、1日あたりの支給額(基本手当日額)は上限が定められています。
沖縄の求人メディア「ジェイウォーム」で60歳以上OK(シニア応援)の求人を見てみる。
受給条件は?
高年齢求職者給付金の受給条件は次のとおりです。以下の条件を全て満たした場合のみ受給することが出来ます。
- 現在失業中である
- 働く意欲を持ち、求職活動が行える状態である
- 雇用保険の被保険者が65歳以上である
- 失業する前の1年間に、雇用保険加入期間へ6ヶ月以上あること
現在失業していることはもちろん、再就職するする意思も必要です。求職中の方であれば、問題にはならないでしょう。年齢も同じく、65歳以上の方なら受給条件をクリアしています。
一方、注意しておきたいのが最後の条件です。退職前の過去1年間で、雇用保険加入期間が最低6ヶ月は必要とされています。これは65歳未満の労働者と同じ条件ですが、もし加入期間が6ヶ月に満たない場合は、高年齢求職者給付金が支給されません。
また、受給可否が判断されるまでは一定の期間(待機期間)があります。受給対象から外れるケースとして、待機期間中に仕事が見つかったり、アルバイト・パートを行った場合などがありますので、手続きを行う際は念頭においておきましょう。
支給額の計算方法
高年齢求職者給付金の支給額は、次の流れで計算する必要があります。
- 賃金日額を計算する(計算式は「退職前6ヶ月間の給与総額÷180」)
- 賃金日額をもとに基本手当日額を計算する(賃金日額に給付率80%~50%を掛け合わせる)
- 基本手当日額に30または50を掛ける
まず賃金日額を算出しなくてはいけません。賃金日額は6ヶ月前の給与総額が基準となります。例えば退職前6ヶ月間で90万円(月15万円)の給与を得ていた場合、賃金日額は5千円です。ただし、賃金日額は上限と下限(年度により変動)がありますので、ハローワークの窓口で確認することをおすすめします。
次に基本手当日額を計算しましょう。高年齢求職者給付金の支給額に関わる重要な要素です。賃金日額に所定の給付率をかけ合わせますが、前職の収入が多い方ほど給付率が低く、少ない方ほど給付率が高く設定されています。賃金日額が5千円の場合、給付率は80%と定められていますので、基本手当日額は4千円です。
そして基本手当日額に30または50を掛け合わせると、高年齢求職者給付金の支給額が分かります。基本手当日額が4千円ですと、支給額は12万円または20万円です。
なお、30または50と説明しましたが、雇用保険加入期間が6ヶ月~1年未満の方は30を、1年以上の方は50を掛けます。実際に計算する際は、まず雇用保険加入期間をチェックしてみましょう。
手続きの方法や流れ
高年齢求職者給付金の手続きは非常に簡単です。以下の流れに沿って手続きしましょう。
- 前の職場から離職票を貰う
- 必要書類などを揃える
- 居住地管轄のハローワークの窓口で手続きをする
- 求職者説明会へ参加する
手続きはハローワークで行いますが、以下のものが必要です。
- 離職票
- 雇用保険証
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関の情報(支店名や口座番号)
- 証明写真2枚
- 印鑑(認印も可)
マイナンバーが必要な点に注意しましょう。マイナンバーカードは身分証明書も兼ねるため、お持ちなら持参をおすすめします。もし分からない時は、役所の窓口(住民課など)で相談し、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行してもらいましょう。
まとめ
人生100年時代といわれていますが、日本では高齢者の働きやすい環境整備が着々と進んでいます。高年齢求職者給付金も制度改革の一つで、所定の条件を満たせば一定の給付金が支給されますし、今の生活水準を保ちつつ安心して求職活動をすることができます。生涯現役で働きたい方は、ぜひ活用しましょう。